各プログラム表題をクリックすると詳細があらわれます。
-
respectable retrospective vol.2
映画祭が担うべき重要な役割の1つに、通常の映画館では観ることのできない作品を上映することが挙げられるであろう。 映画芸術が人に観られて初めて成立するものであるなら、古今東西のこれまでに生み出された無数の作品は、きっと今も観られたがっているはずである。 クラシックフィルムの蒐集家・三品幸博氏の御好意により、その財産とも言える貴重なフィルムコレクションから数篇を上映することで、映画の巡り来た道を見つめ、同時に新鮮な驚きとして出会う機会としたい。
映画と言う表現手段を手に入れるや、作家たちは盛んに「非日常」を演出し始めた。 それは例えばあり得ないほどに幸福な話やおかしな話だったが、その中で不可思議で奇妙な、恐ろしい作品が続々登場することになる。 人は何故恐怖を必要とするのだろう。映画が生まれて百有余年――メリエスのたくらみに驚かされて以来、われわれは眼を開けたまま悪夢を見続けているのかもしれない。



- 不思議な井戸
1903年/16mm(上映は8mmを使用)/モノクロ/フランス/3分 監督:ジョルジュ・メリエス
- トルコの死刑執行人
1903年/16mm(上映は8mmを使用)/モノクロ/フランス/2分 監督:ジョルジュ・メリエス
- 音楽狂
1903年/16mm(上映は8mmを使用)/モノクロ/フランス/2分 監督:ジョルジュ・メリエス
- ゴルフ狂の夢
1920年/モノクロ/アメリカ/16mm(上映は8mmを使用)/17分 監督:バスター・キートン、エディ・クライン 出演バスター・キートン、シビル・シーリー
- ペット
1921年/8mm(上映は8mmを使用)/アニメーション/アメリカ/10分 監督:ウィンザー・マッケイ
- 落胆無用
1921年/16mm(上映は8mmを使用)/モノクロ/アメリカ/26分 監督:フレッド・ニューメイヤー 出演:ハロルド・ロイド、ミルドレッド・デイヴィス
- 午後の網目
1943年/16mm/モノクロ/アメリカ/14分 監督:マヤ・デレン、アレクサンダー・ハミッド 主演:マヤ・デレン、アレクサンダー・ハミッド -
まなざしが紡ぐもの
ルミュエール兄弟が映画を作り始めた時を同じくして誕生したドキュメンタリー映画は、
いつの時代も観る人の心を惹き付ける。
被写体のパーソナルスペースにいとも簡単に侵入してしまうカメラは、潜在している窃視性を刺激し、
画面に自己投影したり、咄嗟の防御反応から身を引いたりする。また、フィクションかノンフィクションか
という灰色の間で揺れ動く心理は、いつも魅力的だ。
今回映画祭で特集するのが、ホンマタカシ監督の「きわめてよいふうけい」と佐藤真監督の「花子」。
壮絶過ぎる事件から生還した中平卓馬と、食べ残しで斬新なアートをする今村花子をクローズアップ
している。静かな時間の中での穏やかな笑顔や、心悸昂進するほどの感情表現は、真っ直ぐで曇りの
ないまなざしと供に、心を直に貫いてくる。
ドキュメンタリー映画というと、社会的問題を取り上げた作品が多く、教育的な所で発展してきた歴史
から何となく難しいイメージがあるが、繰り返される日々の生活描写は微笑ましく、観終わった後に
不思議な感覚が残る。
ホンマの作品は、設定を作った中で被写体を動かし、佐藤の作品は自分が透明になるまで被写体の
生活に入り込むことが多いという。いずれにせよ、作品を作る過程は自分自身と強烈に向き合う瞬間
である。
現代は、全くの人間関係希薄、1対1の関係すら危うく、脆い。被写体やその周りを囲む生活、
さらにこれらを包括する社会情勢と向き合うドキュメンタリー映画は今後どう変化していくのか、
そして次世代はどんな映像を撮れるのか、興味がかき立てられる時代が来た。数十分の作品を生み出すために、監督は何百時間もカメラを廻す。僅かな間に繰り広げられる「他人の日常」を、緊張し息をのみ見入ってしまうのは、濃厚な時間や空気、さらには撮す側の息づかいまでをもフィルムに焼き付けてしまうドキュメンタリーという映画の持つ力に他ならない。淡々とした静かな眼差しで紡がれた作品は、映画が終わっても変わらず繰り返されているであろう彼や彼女の日常のように、ささやかな幸せを私たちに与えてくれる。

- きわめてよいふうけい
撮影・監督/ホンマタカシ 2004年/16ミリ/カラー/40分
写真家ホンマタカシが今回監督としてカメラを向けたのは、伝説の写真家、中平卓馬だった。かつて先進的な言葉と写真によって既存の写真表現を挑発してきた中平は、1977年にそれまでの記憶を一切失った。そして今…、朝起きて、日記を書き、写真を撮りに出掛ける、失った記憶の中で、それでも生き続ける行為を繰り返す日々。そんな中平の「現在」を見つめたポートレートムービー。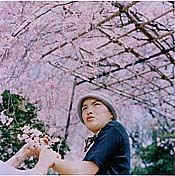
- 花子
2001年/35ミリ(上映は16ミリを使用)/スタンダード/カラー/60分
監督/佐藤真 撮影/大津幸太郎 録音/弦巻裕 編集/泰岳志 主題歌/忌野清志郎
今村花子22才は「たべものアート」と母親が命名した「作品」製作を毎日続けている。夕食のおかずを畳やお盆の上に並べる花子、その「作品」をひたすら写真に撮り続ける母親のこだわり、それを見守る父、少し距離を置く姉。『阿賀に生きる』でデビュー以来『まひるのほし』『SELF AND OHERS』と優れたドキュメンタリー作品を作り続ける佐藤真監督が花子のアートを通して広がる今井家の日常を静かなまなざしで綴った作品。 -
新しい才能に出会う 金の笹かま編
新しい才能 インディーズ作品との出会いは10年位前、今思うとそれが塚本晋也だったり、雨宮慶太だったり
佐藤信介だったり。
教えてくれたのは当時東北学院大学で映画をつくっていた人たち。
その時から、商業映画、劇上映画とは違う新しい楽しみを手に入れた。お気に入りは「ダイアモンドの月」という作品だった。
初めて持ったカメラはFIJIの450、8ミリで撮した風景は、空想の世界のようにその時
の空気をフィルムに焼き付けて今も棚に並んでいる。覗いたカメラの四角いフレーム<は魔法の箱のようだった。それからも、たくさんのインディーズ作品を教えられ、観てきた。
今年も100本以上の作品を観る機会を与えてもらった。
今回はプログラムを作ることが目標での作品選出。思い入れと客観性とのせめぎ合い
で1本観ては感想を書きながら、数週間の後に今回の上映作品を決めさせてもらった。
送ってくださった方々があって初めて成り立つプログラムを映画祭で立ち上げること
ができる幸せをぜひたくさんの人に観てもらいたい。そしてここで観た作品が、何年
か後もこの監督たちの作品を見続けるきっかけであったり、自身が映画を撮り始める
きっかけであればさらなる幸せである。当日はこのプログラムの監督たちに、塩田明彦監督、さらにはこれからこのプログラムに作品が上映される
やもしれない観客のみなさんで、作品の話、映画の話をおおいに交わしてもらいたい。
僕はその風景を、あの8ミリカメラを覗いた時と同じ気持ちで、9月18日この眼に焼き付けたい。ゲスト(予定)塩田明彦(映画監督)
新しい才能の発見などと書くと仰々しいが、要はDVカメラの急速な普及により映画を撮るということが特別なものではなくなり、またアマチュアとプロの境界線もボーダレスになった。それらの作品群から短篇映画の面白さを知ってもらうというコンペティションという形式に疑問を呈した仙台短篇映画祭の新たな挑戦が始まった。PART1「金の笹かま編」、PART2「プラチナの牛タン編」と題し、ゲストに塩田明彦監督を迎え、上映作家たち、そして観客をも巻き込んでの上映&トークで「新たな才能」の魅力を探る拡大プログラム。
- ニセの虹
監督:山藤みほ2004年/カラー/DV/27分
ストーリー:心を閉ざしバスタブにこもる兄は、バスタブから想像の旅に出掛けている。その面倒を見る弟もまた、元気な自分を保つための楽しい妄想癖がある。そんな弟がある日恋をした…。
プロフィール:1971年、生まれ。多摩美術大学卒業後、10分程度のイメージ的映像作品を複数本制作。映画館受付をしながら2003年『ジェットカゼジェリ→』で脚本にも挑戦。同作品が第6回インディーズムービーフェスティバル、第3回仙台短篇映画祭で入賞。
- 萠童
監督:上野比佐子2004年/カラー/5分
ストーリー:用意されて居た環境で安穏と暮らして来た子供が、変化に気付かない振りを続ける事の痛みを知り、目を背けて居た本当の自分と向き合う事で、大人になる一歩を踏み出す事が出来る話。
プロフィール:大阪出身、大阪芸術大学映像学科4回生、高校からアニメーション製作部に所属
- 化けて出てこい
監督:田中博之2003年/カラー/DV/10分
ストーリー:富士リカは白血病だった。人生の九割を入院で過ごしていた。山田君は心臓が弱かった。二人は賭けをした。骨と心臓を。リカが死ねば、山田君は生きる。山田君が死ねば、リカは生きる。「生きる事は、外に出る事」それがリカの青春。リカは、山田君を殺してでも生きたかった。殺す気の恋愛映画。
プロフィール:1982年、京都府宮津市生まれ。2000年より、名古屋にて映画制作開始。西東京映画祭、イメージフォーラムフェスティバル、東京国際ファンタスティック映画祭、PFFアワード、ひろしま映像展など、様々な映画祭で注目される。CSデジタル放送にて作品放送。NHK教育・中学生日記の脚本執筆。1日で100人の女にビンタされる。
- ラディカルダンス
監督:渡邉 剛 2004年/カラー/20分
作品プロフィール:この映画には、エンドロールが付いていないので、この場を借りて紹介させいただきます。 出演 関口/山崎さん/工藤さん 協力 富田さん/神崎さん/大城さん/鈴木さん/杉村さん阿部/チカさん そしてこの映画のために時間を割いてくれた全ての皆さんに感謝します。
プロフィール: 昭和55年東京都生まれ。NCW修了・いずみさのオフシアター映画祭入選 第五回水戸短編映像際準グランプリ・読売テレビにて作品放映
- ロス:タイム:ライフ
(英題:Life in Additionaltime) 2003年/カラー/DV16:9/9分30秒
(C)BS-i、goggle Inc./BS-i、BSフジ共同番組「68」美少年Hi!シリーズ 監督、脚本、編集、VFX:筧昌也 撮影:モリカツ 録音:浅田将助 音楽:水野修一 CG:海老沢憲一 出演:虎牙光揮、中村麻美、岡野進一郎、新宿ミサイル 他
ストーリー: もしも、人生にロスタイムがあったら?裏社会で仕事をしている修一はこの仕事を最 後にアシを洗おうとしていた。しかしそれを告げた途端、突然銃口を向けられる。轟 く銃声。弾丸は刻一刻と迫ってくる。するとその時、何故か、サッカーの審判団が駆 け寄って来た!彼にはなんと「人生のロスタイム」が与えられたのだ。
プロフィール: 1977年東京生まれ。映像ディレクター、イラストレーター。98年「スクラップ」、00年 「ハライセ」と続けてゆうばり映画祭に入選。仕事ではモーショングラフィックス、 2Dアニメを中心に活動。03年、映画「美女缶」完成。ゆうばり映画祭2003オフシアター 部門グランプリ他多数受賞。2004年10月、渋谷シネ・ラ・セットにて劇場公開。 -
新しい才能に出会う プラチナの牛タン編
ゲスト(予定)塩田明彦(映画監督)
新しい才能の発見などと書くと仰々しいが、要はDVカメラの急速な普及により映画を撮るということが特別なものではなくなり、またアマチュアとプロの境界線もボーダレスになった。それらの作品群から短篇映画の面白さを知ってもらうというコンペティションという形式に疑問を呈した仙台短篇映画祭の新たな挑戦が始まった。PART1「金の笹かま編」、PART2「プラチナの牛タン編」と題し、ゲストに塩田明彦監督を迎え、上映作家たち、そして観客をも巻き込んでの上映&トークで「新たな才能」の魅力を探る拡大プログラム。
- 断面
監督:山下敦弘1998年/8mm(DV)/カラー/日本/20分
作品プロフィール:「どんてん生活」のエチチュードとして撮影した8mm作品。しかしこれは後に黒沢 清に「傑作だ!」と言わしめる作品となった。二人の青年のほのかな友愛を描くア メ リカンニューシネマ風のバディ喜劇。
プロフィール: 1976年愛知県生まれ。95年大阪芸術大学映像学科に進学、先輩である熊切和嘉の 『鬼畜 大宴会』にスタッフとして参加する。在学中に何本かの短篇を発表後99年卒業制作 と して完成させた『どんてん生活』が2000年夕張ファンタスティック映画祭オフシア ター 部門のグランプリを受賞。02年『ばかの箱船』03年『リアリズムの宿』、そして現 在新作を準備中と、今一番勢いのある映画監督である。
- マリコ三十騎
監督:真利子哲也 2004年/カラー/DV(8mmテレシネ)/ 26分
ストーリー: 大学の学部拡大を目論む大学当局にとって邪魔となった学生会館。朝まで飲んで機 動 隊に囲まれたりと、思い出深い。一方にそびえ立つビル。食堂には雑誌から飛び出 たような美男美女が集まり、飯が食える雰囲気ではなかった。壊される学館思って憤 怒した…すべては8mmの投影する一つの物語。
プロフィール: 1981年東京都生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業。同時にイメージフォーラム付属研究所卒業。その後、友人の紹介で派遣会社に勤めたが、結局無職に落ち着く。サラリーマン経験が逆に引き金となり、今後は映像による何らかの展開を目論んでいる。『極東のマンション』(03)で仙台短篇映画祭2003コンペティショングランプリほか数多くの賞を受賞。
- オリエンテ・リング
脚本・監督/冨永昌敬 出演/福津屋兼蔵、不二子ほか2004年/DV/15分
作品プロフィール:劇作家・宮沢章夫氏が主宰する遊園地再生事業団のオムニバス映画、『be found dead』の第4話として制作。文字通り「死体発見」というコンセプトのもと、所属タ レントの愛人の自殺遺体を捜索する芸能プロダクション社員の奔走を描く。サウンドトラックはジョナス・ メカスやダニエル・シュミットとのコラボレーションでも知られるCOMBO PIANOが担 当。
- テトラポッド・レポート
脚本・監督/冨永昌敬 出演/福津泰至、木村文ほか2003年/DV/15分
作品プロフィール:伝説のクレイアニメーション映画「虚穴遊戯」の上映会場。最前列の座席で、ひと 組の男女の死体が発見された。「心中である」「陰謀である」、ふたつの説を巡るも うひと組の男女の途方もないやりとりは、獄中の<監督>から寄せられた肉声テープ によって決着を迎えることになる。
冨永昌敬(とみながまさのり)プロフィール: 75年愛媛県生まれ。99年日本大学芸術学部映画学科卒業。『ドルメン』(99) が2000年オバーハウゼン国際短編映画祭にて審査員奨励賞を、『VICUNAS/ビクー ニャ』(02)が2002年水戸短編映像祭グランプリを受賞。他に『亀虫』(03)など。 現在は日本の最先鋭のジャズを追うドキュメンタリーを制作中であるとともに、初の 長編劇映画を準備中。